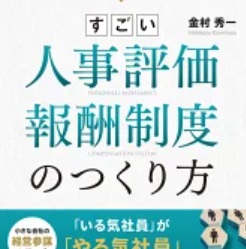今日は人事評価の会議でした。評価する側として参加したのですが、やはり目標設定というのは本当に難しいものだと改めて感じました。
難しすぎる目標を設定してしまうと、本人のやる気を削いでしまうし、逆に簡単すぎる目標では挑戦する意味がなくなってしまう。
適度な難易度で、達成すれば本人も成長を実感できるような目標を立てることが理想なのですが、これがなかなかうまくいかないのです。
営業職であれば売上額や契約件数といった客観的な指標があるので比較的設定しやすいのですが、そうでない職種の場合は「成果」を数値化するのが難しく、どうしても曖昧な表現になりがちです。
たとえば企画職や事務職では、努力や工夫が目に見える形で表れにくいので、どのような目標を立てさせるか悩みます。
また、評価する側としては公平性も意識しなければならず、同じ部署内で似たような業務をしている人たちに対して、バランスの取れた目標を提示する必要があります。
誰かだけが極端に厳しい目標を課されてしまうと不満が生まれるし、逆に甘すぎる目標を与えられた人がいると周囲の士気が下がってしまう。
結局、目標設定は本人の能力や経験、そして将来的な成長を見据えた上で調整していくしかないのですが、これが一番頭を悩ませるところです。
一方で、評価される側の立場を考えると、ある意味では楽なのかもしれません。提示された目標に対して努力すればいいわけですし、評価の基準を自分で決める必要はないからです。
ただし、モチベーションを維持するのは簡単ではありません。人によって何にモチベーションを感じるかはまったく違います。昇進や昇給といった分かりやすい報酬にやる気を見出す人もいれば、仕事を通じて自分の成長を実感することに喜びを感じる人もいる。
中には「周囲からの評価」や「チームへの貢献」に価値を置く人もいて、本当に多様です。評価する側としては、その人が何にモチベーションを持っているのかを理解し、それに沿った目標を提示することが重要なのだと思います。
今日の会議を通じて感じたのは、人事評価というのは単なる点数付けではなく、組織全体の雰囲気や働く人の意欲を左右する大事な仕組みだということです。目標設定ひとつで人の気持ちは大きく変わるし、評価の仕方次第でチームの空気も良くも悪くもなる。
だからこそ、評価する側には大きな責任があるのだと改めて実感しました。これからも試行錯誤しながら、本人の成長と組織の成果を両立できるような目標設定を考えていきたいと思います。